税理士日記
税理士日記
副業収入300万円以下を雑所得とするパブコメ案撤回
2022/10/31 15:49:33
副業収入300万円以下を雑所得とするパブコメ案撤回
異例の7,059通にものぼるパブコメ意見が寄せられた雑所得を例示する改正所得税基本通達は、事業所得か業務に係る雑所得等かの区分判断について、記帳・帳簿書類を保存しているかどうかで整理することで落ち着きました。パブコメ案の副業に係る収入金額300万円基準により所得区分を判定することに多くの反対意見が寄せられたこともあり、国税庁は大幅な修正を強いられる結果となりました。パブコメ意見とそれに国税庁の回答を順にみていくと、主たる所得か否かを基準とすることについては反対意見が相次ぎました。真っ向から「本業か副業かで所得区分を判断すべきではない」との否定や、「どのような所得が主たる所得に該当するのか不明確」「開業届が提出されているのであれば、副業であっても、事業所得と取り扱うべき」と否定的な意見が集中しました。さらには「フリーランスの場合は、契約形態によって所得区分が分かれる場合がありますが、この場合、主たる所得はどうなるのか」「真面目に記帳等をしている者は、収入金額300万円以下の副業であっても事業所得と取り扱うべきではないか」といった疑問の声もありました。
さすがにこうした多数の声を無視するわけにいかず、国税当局は、ご意見を踏まえ、主たる所得かどうかで判定するという取扱いを撤回するとして、「所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定すること」へと変更します。この修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則的には、事業所得に区分されることなります。(例外もあります)
パブコメ意見の力は、大したものですね。この300万円の基準は、かなり荒っぽい形式基準だと思います。なかなか、ある一定の基準で、事業活動の中身について評価するのは、難しいです。事業活動であることを客観的にうまく定義できないですね。庶民の生活の知恵は、許容範囲として頂けないでしょうか。
生命保険金の非課税枠の拡大要望
2022/10/24 18:04:40
生命保険協会が生命保険金の非課税枠の拡大要望
節税の観点から頭をひねってアイデアを出してきた生命保険業界ですが、令和5年度税制改正要望で生命保険協会は、遺族の生活資金確保のため相互扶助の原理に基づいて、死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げを要望しています。死亡保険金は、保険金受取人が保険金請求権を固有の権利として原始的に取得し、保険会社から直接受け取るものであり、相続税創設当初においては非課税として取り扱われていました。その後、死亡保険金を相続財産と「みなす」ことにより「みなし相続財産」として課税対象に取り込むこととされた結果、現在では、すべての法定相続人につき1人当たり500万円を非課税とすることとされています。
相続財産の約4割は土地・家屋など換金性の低い資産で占められていますが、これらは残された家族が居住の用に供するためのものであって、生活資金の柱となるのは、「遺族年金」や「現預金」、「死亡保険金」などとなっているのが実情です。しかし、未成年の子がいる母子遺族世帯の場合、これだけでは生活費を賄うことができず、土地・家屋など相続財産を切り崩して生活資金を確保している事例も散見されます。
そこで、生命保険協会は、「法定相続人数×500万円」という現行の限度額に「配偶者分500万円」と「未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを税制改正要望として打ち出しています。
相続税の生命保険金の非課税が拡大されると、確かに母子遺族世帯などは助かります。生命保険料を所得控除しない代わりに、保険金を非課税にすることも検討に値すると思います。
総務省、インボイス制度広報等協力を地方団体に要請
2022/09/20 14:29:29
総務省、インボイス制度広報等協力を地方団体に要請
総務省はこのほど、消費税のインボイス制度の広報・周知に、地方団体がより一層主体的かつ積極的に対応するよう、都道府県を通じて全国の地方団体に通知しました(令和4年8月5日・総税都第58号)。現在、インボイス発行事業者の登録件数は7月末時点で個人・法人を合わせて80万件程度と見られ、全事業者の2割に遠く及ばない状況です。来年の2月、3月で登録申請者が集中し、登録事務が滞留することのないよう、早めの申請を事業者に促すことが狙いと見られます。
通知では、地方団体に(1)税務署が開催する説明会への協力と(2)地方団体自らが主体的に行う広報・周知の2点を主に要請しています。(1)では、現在、各地の税務署において開催されている事業者向けの説明会の実施に当たり、税務署からの相談・依頼に応じ、開催の周知、開催場所の調整について、地方団体内において連携し、積極的に協力することを要請しています。また、(2)では、地方団体内の商工担当部局が定例的に開催している事業者向け説明会を活用し、税務署によるインボイス制度の説明の機会を積極的に設けることを要望しています。その際には、インボイス制度の内容に加え、制度対応を後押しする事業者向けの助成金や補助金の支援措置についても説明するなど、事業者にとって興味を引く説明会となるよう工夫することも合わせて要請しています。
弊事務所では、消費税の課税事業者である法人・個人の方には、適格請求書発行事業者の登録申請(インボイスの申請)をお勧めしております。手続きは、弊事務所が代理で申請しております。いろんなケースが想定され、なかなか説明が難しいときもあります。
消費税のインボイス制度のアンケート
2022/09/07 11:32:45
消費税のインボイス制度のアンケート
来年10月の消費税のインボイス導入まで1年余りと迫ってきたものの、事業者の準備や取引先への対応が進んでいないことが分かりました。東京商工リサーチが8月1日から9日に実施した「インボイス制度」の企業向けアンケート調査(回答数6,441社)によると、「インボイス制度そのものを知らない」は7.5%で認知度は高まっていますが、その準備や対応は鈍く、まだ半数近くの46.7%の企業が取引方針を決めていない実態も分かりました。周知のとおり、インボイスを来年10月から発行するには原則、来年3月末までに登録申請する必要があります。経過措置があるものの、免税事業者のままだとインボイスを発行できず、(免税事業者から仕入れた)売上先の事業者は仕入税額を控除できないために納税額が大きくなります。これを避けたい事業者が、免税事業者との取引の解消や値下げを要求する懸念があります。一方で免税事業者は、課税事業者を選択すると消費税の納税義務が生じ、小規模事業者ほどその板挟みに苦悩しています。
アンケート結果をみると、インボイス制度の導入後、免税事業者との取引について、「これまで通り」が41.2%である一方、全体の1割近くの9.8%は「免税事業者とは取引しない」と回答し取引中止を示唆するほか、「取引価格を引き下げる」も2.1%あった。ただし、46.7%が「検討中」としており、半数近くは取引方針を決めかねているようです。なお、取引中止を回答した企業は、「大企業」が6.4%、中小企業が10.4%で、中小企業が大企業を4ポイント上回りました。取引継続は資金負担が生じることもあるだけに中小企業のシビアな回答が目立ちました。
免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出して、インボイスの番号をとると、自動的に課税事業者となります。消費税の申告をしなければならなくなります。今まで消費税の10%部分のみが、儲けと言われていた方々は、青ざめておられます。今までの取引先と商売をしたいのに、手取りはなしということになります。何か、救済策が欲しいところです。
相続土地の浄化・改善費用相当額の控除
2022/08/29 10:13:38
相続土地の浄化・改善費用相当額の控除
相続した土地の評価に当たって、その評価額から土地の浄化・改善費用相当額を控除できるか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は、相続開始日に土壌汚染のある土地と認められることから、同相当額を控除すべきと判断し、原処分を全部取り消しました(令和3年12月1日裁決)。この事件は、被相続人から土地を相続した審査請求人が、相続財産の土地は土壌汚染地であるとして、その土地の評価について浄化・改善費用に相当する金額を控除して相続税の申告をしたのが発端です。これに対して原処分庁は、土壌汚染対策法に規定する汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域に指定等がされていないため、これらの費用の負担が確実に発生するとはいえないとして更正処分等をしたものです。
審判所は、相続開始日に土壌汚染対策法上の基準を超える特定有害物質を地中に含有していたことが認められ、土壌汚染のある土地と認めるのが相当と判断しました。各土地の評価に当たっては浄化・改善費用相当額を控除すべきであると指摘しました。さらに、各土地やその周辺の状況、土壌汚染の状況から、各土地について最有効使用ができる最も合理的な土壌汚染の除去等の措置は掘削除去であると認められ、請求人が主張する土壌汚染対策工事の見積額の算定過程にも特段不合理な点は見当たらないことから、浄化・改善費用の金額として相当と認められるとの見解も示しています。
土地の評価について、実態に則した判断がなされたようです。土地評価の実務では、悩ましい事象は多々起きます。何度も現地へ行って、判断されたものと思います。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
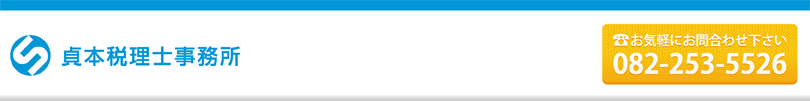



 RSS 2.0
RSS 2.0