税理士日記
税理士日記
新年ご挨拶
2016/01/03 14:55:49
新年ご挨拶
新年あけましておめでとうございます。旧年中は、大変お世話になり、ありがとうございました。
今年も、皆様のお役にたてるように、努力してまいります。
よろしくお願い申し上げます。
今年は、サービスの幅を広げ、企業の相続・事業承継や家族信託などに、より一層取り組みたいと思っております。
もちろん、従来からの企業の経営相談、個人の相続・贈与相談、社会福祉法人などの会計相談も引き続き、注力してまいります。
皆様と一緒に汗をながして、頑張ります。
企業版ふるさと納税
2015/12/18 14:46:22
企業版ふるさと納税の創設
政府・与党は平成28年度税制改正の素案を12月初めにまとめ、地方税関係の焦点の一つとなっていた、いわゆる「企業版ふるさと納税」の創設が確実となったことが分かりました。これは、地方創生の一環として、自治体が行う一定の事業に対して法人が行った寄附について、法人住民税と法人税の税額控除が認められるものです。企業版ふるさと納税の対象となるのは、地方版総合戦略を策定する都道府県と市町村が地域再生計画に基づいて行う認定事業とされました。ただし、寄附をする法人の本社など主たる事務所が立地する自治体への寄附や、東京・大阪・名古屋を含む三大都市圏にあり、地方交付税の不交付団体である自治体への寄附は対象から除外されます。
このような自治体の認定事業に法人が寄附した場合には、その寄附額を法人の所得計算上損金に算入するとともに、新たに法人住民税と法人税からそれぞれ税額控除を認める課税の特例が講じられます。つまり、寄附額の損金算入によってその約3割が減税となる現行制度に加え、これとは別に3割の税額控除が認められることとなり、減税効果は現行の倍となることが見込まれます。企業の実質負担は寄附額の約4割となる制度設計です。
詳細は与党の平成28年度税制改正大綱に盛り込まれます。
企業版にもご当地の産品などが送られてくるのでしょうか? 注目しましょう。
タワ−マンション
2015/11/24 15:36:47
タワ−マンション節税にメス?
10月27日の政府税制調査会において、タワーマンションを使った過度の節税策が議論の俎上にあがりました。この日の政府税調では資産課税が議論され、多額の資産を持っている資産家だけが利用できる過度の節税策は課税の公平性の面から問題として、タワーマンションを使った節税策が取り上げられ、時価と評価額のかい離が多き過ぎるものについては、通達を改めるか、別途措置すべきとして、見直しを図るべきとの意見が出ました。
区分所有建物であるマンションの建物の評価は、一般に時価よりも低くなる建物の固定資産税評価額を用いて行われます。
また、その敷地の評価は、路線価方式または倍率方式により評価されたそのマンションの敷地全体の評価額に、その部屋の敷地権割合を乗じて行います。
これら区分所有建物の価額と敷地の価額の合計がマンションの評価額になるが、都心のタワーマンションの場合、その評価額は時価を著しく下回る傾向にあり、過度の節税に用いられるケースが後を絶たないということです。
現行、家屋の評価は、固定資産税評価に準拠しているものの、実質的に租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合には、財産評価基本通達6項が活用されています。
財産評価基本通達
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
これまでもタワーマンションを用いた過度の節税は、問題視されていましたが、今後は何某かの対応策が講じられることも想定され、その動向が注目されます。
節税方法は、世の中に出回り目立つと、メスが入るものなんでしょうか?
マイナンバ−制度
2015/09/18 17:48:13
金融機関等でのマイナンバ−の利用
今年5月の日本年金機構における個人情報流失問題で、成立が危ぶまれていた改正マイナンバー・個人情報保護法とその整備法が、参議院での修正を経て、9月3日に衆議院で成立しました。整備法の中に盛り込まれ、金融機関等に対して個人番号・法人番号で預貯金情報を検索できるように管理することを義務付ける改正国税通則法は、平成30年1月から実施される見込みです。改正法は、平成28年1月から番号利用が始まるマイナンバー制度の利用範囲を広げるものです。例えば(1)社会保障制度における資力調査や国税・地方税の税務調査において金融機関の持つ預貯金情報を利用できるほか、(2)医療分野では、特定健康診査情報の管理や予防接種履歴の地方公共団体間の情報交換――などに番号を利用できます。(1)の預貯金情報とは、預貯金者の氏名や名称、住所又は居所その他預貯金等のことであり、個人番号や法人番号を使って、複数の金融機関等の口座残高を集計したり、預貯金の出入り等を把握することができるようになります。
とはいえ、改正法は預貯金者に対してマイナンバーを金融機関に告知することを義務化していないので、多くの預貯金情報に番号が紐づけられなければ、税務調査での利用は限定的なものとなります。このため、改正法は、施行から3年を目途に必要な措置を講じるとの見直し規定もあります。
施行から3年を目途に金融機関でマイナンバ−を告知することが義務化されたら、税務調査などで利用されることになります。この件の行方を注視していく必要があります。
マイナンバ−
2015/08/22 10:02:35
マイナンバ−
平成28年1月から制度の施行が予定されているマイナンバー制度。その番号の通知が、平成27年10月に開始されます。マイナンバー制度が開始されると、事業者は、社会保障や税の手続きのために、従業員やその家族のマイナンバーを取得し、適切に管理・保管しなければなりません。
今回は、マイナンバー制度の概要と税務関係書類等について確認し、個人情報の取扱いについて特例的な対応方法が認められる中小規模事業者についても確認しましょう。
【マイナンバー制度の目的】
マイナンバー制度は、いわゆる番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)に基づいて、マイナンバー(個人番号)を効率的に管理、運用することにより、「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」を目的としています。
ただし、マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにしか使うことはできないとされています。
【税務関係の申告書等にマイナンバーを記載】
制度が施行されると税務関係の書類についてマイナンバーの記載が必要となり、例えば、申告書、申請書、届出書、法定調書等に提出する本人のマイナンバー、または法人番号を記載することになります。
給与所得の源泉徴収票や、給与支払報告書については、(1)支払者のマイナンバーまたは法人番号(2)支払いを受ける者のマイナンバー(3)控除対象配偶者および扶養親族のマイナンバー等を記載します。
【扶養控除等申告書に記載するマイナンバーの収集】
前述のとおり、番号が利用できる範囲は、法律や自治体の条例で定められた、社会保障・税・災害対策に制限されますが、事業主は、必要とされる従業員やその家族のマイナンバーを収集しなければなりません。
また、マイナンバーは、あくまでも番号法に規定されている事務処理のために、収集、管理されるものであり、事業主はその番号の管理を徹底することが求められます。
この点に関連して、番号の利用が開始される平成28年1月以前に、従業員からマイナンバーを収集することは可能なのかが問題視されましたが、内閣官房では、マイナンバー関係事務のために、あらかじめマイナンバーを収集することは可能であることを明らかにしています。
例えば、番号の通知が開始される平成27年10月以降、年末までの間に、従業員に平成28年分の扶養控除等申告書の提出を求める際、個人番号関係事務実施者となる事業主が従業員からマイナンバーを収集することは可能です。
【マイナンバー導入のためのチェックリスト】
現在、行政機関は、マイナンバー制度の周知に力を入れていますが、内閣官房では「マイナンバー導入チェックリスト」を公表しています。
そこでは、従業員数の少ない事業者(いわゆる中小規模事業者(事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者のうち一定の者を除く事業者))について、以下の内容について確認するよう周知が図られています。
○担当者の明確化と番号の取得
■マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。
■マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
■マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
(1)顔写真の付いている「個人番号カード」か、(2)10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
○マイナンバーの管理・保管
■マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。
■パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。
■従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
○従業員の皆さんへの確認事項
■チェックリストの裏面「マイナンバー制度、はじまります。」を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。
まだまだ、どこまで徹底するのか、どのような取扱か、はっきりしないところもありますが、この時期に概要を知っておくことは大切です。準備しておきましょう。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
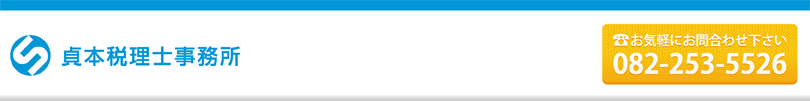



 RSS 2.0
RSS 2.0