税理士日記
税理士日記
企業会計基準34号「リースに関する会計基準」等の公表
2024/09/24 18:37:22
企業会計基準34号「リースに関する会計基準」等の公表
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月13日、企業会計基準34号「リースに関する会計基準」等を公表しました。適用時期は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとされ、2025年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からの早期適用も認めています。改正リース会計基準等は、現行のリース会計基準等とは大きく異なります。国際的な会計基準との整合性の観点から、借手のリースの費用配分の方法について、IFRS16号「リース」と同様、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかに関係なく、すべてのリースについて資産及び負債を計上することとしています。連結財務諸表だけでなく、個別財務諸表についても適用されるため、仮に税務上の取扱いが変更された場合には、上場会社や会社法上の大会社だけでなく、中小企業にも影響を及ぼすことになります。
リース会計基準等の改正に伴う税制上の措置は、令和7年度税制改正での大きな論点の一つとなりそうです。
なお、日本公認会計士協会も同日、改正リース会計基準等の公表に伴い、業種別監査委員会報告19号「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」など、5本の実務指針等を改正し、公表しました。リース資産を「使用権資産」、リース債務を「リース負債」に変更するなどの見直しが行われています。
この改正リース会計基準は、IFRS(国際会計基準)と同様の処理をするとなると、中小企業にとっては、記帳面においてもハードルが高いものとなりそうです。IFRSでは、通常の家賃もリースとして取扱う処理があったと記憶しております。未だ、私はこの度の改正リース会計の内容の詳細は把握しておりません。ただ、やっかいなものがやって来たとは感じてております。
インド法人との取引に係る料金 源泉所得税について
2024/08/23 16:50:07
インド法人との取引に係る料金 源泉所得税について
内国法人がインドの法人3社と取引し、料金を支払ったところ、租税条約に基づき国内源泉所得に該当するため、源泉徴収をすべきであったとして否認を受けました。審判所は、これらの取引は源泉徴収対象と認めながらも、一部の取引に係る源泉徴収税額の計算方法は課税庁の誤りとして取り消していたことが分かりました(令和5年8月15日裁決)。同裁決によると、家電等のスマホによる遠隔操作等のサービスを提供するX社は、インド法人のJ社、K社、L社とそれぞれ取引を行い、その代金を支払いました。課税庁はこの取引について、日印租税条約に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当するため国内源泉所得となり、源泉徴収が必要になると指摘して課税処分を行いました。X社はこの処分を不服として審査請求に及んだというものです。
一方、X社は、3社のうち1社はX社が出資するLLP(リミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ)であり、取引の対価は給与等に当たるとしました。その他2社との取引もソフトウェアの譲渡対価及びデザイン料であり、「技術上の役務に対する料金」には該当しないと主張しました。これに対し審判所は、いずれの取引も「技術上の役務に対する料金」と認め、X社の主張を斥けたものの、課税庁がK社との取引をグロスアップ計算(手取り額から税込額を逆算する方法)により源泉所得税の計算を行っていた部分のみ誤りと判断しました。この部分についての課税処分のみ取り消しました。
上記のようにインド法人に支払う報酬(使用料)に関する源泉徴収については、日印租税条約の規定により使用料を支払う側が源泉所得税を納税することになっています。(債務者主義)注意されください。
USCPAのライセンス
2024/08/01 16:36:36
USCPAのライセンス
今年の2月にアメリカ合衆国のワシントン州で公認会計士(USCPA)のライセンスを登録しました。アメリカ合衆国の公認会計士は、ライセンスを継続するためには、継続教育をう受けなければなりません。3年で120単位、1年最低20単位、さらに、倫理の単位も含まなければなりません。継続教育の要件を満たさなければ、ライセンスが取消となります。アメリカ合衆国の公認会計士協会は、それだけ厳重に資格の質を保つために、制度化しています。内容は、会計、税法、監査、倫理、ファイナンス、ビジネスマネジメント、情報技術など多岐にわたります。私はBeckerのOn−Demandの授業を少しずつ毎朝見て、単位を取得しています。英語が苦手な私にとっては、結構大変です。
過大な専従者給与
2024/07/23 18:44:08
過大な専従者給与
診療所を営む医師が、看護師及び事務長として診療所の業務に従事する配偶者に対し、年額1,800万円の青色専従者給与を支払っていたところ、適正額ではないとして否認された事案の控訴審の東京高裁は、配偶者に対する給与が労務の対価として適正額を超えると判断した一審・長野地裁の判決を支持、課税処分を適法と認めていたことが分かりました(令和5年8月3日判決)。同判決によると、内科等の診療所を営む医師のXは、平成28年から平成30年の3年間において、看護師等として診療所の業務に従事する配偶者への青色事業専従者給与を年額1,800万円として所得税等の確定申告を行いました。課税庁はこの金額を一部否認、増額更正処分等を行ったところ、Xは処分を不服として提訴しました。一審・長野地裁令和4年12月9日判決は、労務の対価として相当とは認められないとして、年間約790万円から820万円を超える額は必要経費には算入できないとして、Xの請求を棄却しました。
Xはこの判決をなお不服として控訴しました。控訴審の東京高裁は、配偶者が看護師兼事務長として責任のある業務を担当し、労務に従事した時間もある程度長時間に及んでいたことはうかがえるものの、このことを客観的に裏付ける証拠がなく、専従者給与の額と労務との対価関係が明確であるとはいえないなどと判示し、課税処分を取り消すべき違法は認められないと判断しました。Xの控訴を棄却しました。
よくある話です。配偶者の給与を大きくして節税を図っていると思われます。しかし、配偶者が充分に働いているのなら、労働を客観的に裏付ける証拠をしっかり残せばよいということになります。タイムカード、看護師としての役割の足跡、事務の仕事の足跡などしっかり管理しておきましょう。
自筆証書遺言書保管制度利用の保管申請件数7万超
2024/06/26 17:16:15
自筆証書遺言書保管制度利用の保管申請件数が7万件超
法務省民事局によると、今年3月末現在、自筆証書遺言書保管制度を利用した保管申請件数と実際に遺言が保管されている件数が、ともに7万件を超えたことが分かりました。遺言には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、うち自筆証書遺言は遺言者本人のみで手軽に作成でき自由度の高いものですが、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされるおそれが指摘されたことから、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)が保管して、その原本及びデータを長期間適正に管理する「遺言書保管制度」が令和2年7月10日からスタートしました。
毎年の申請状況をみると、令和2年が1万2,631件、3年が1万7,002件、4年が1万6,802件、5年が1万9,336件、そして6年が3月末までで5,448件となり、開始からの累計で7万1,219件と7万件を超え、法務局が申請書類を確認して保管している件数も7万1,033件とこちらも7万件を突破してます。
同制度の利用にあたっては、民法968条に沿った自筆証書遺言に限られ、財産目録以外の全文と作成日付及び遺言者氏名を自書し、押印します。財産目録はパソコンを利用し不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法でもよいです。ただし、目録の全ページに署名押印する必要があります。遺言者の死亡後、法務局から、遺言書の存在が相続人等に通知されます。通知には「指定者通知」と「関係遺言書保管通知」があり、遺言者があらかじめ指定しておく指定者通知は3名とされ、相続手続をサポートする者等も通知対象となります。
自筆証書遺言を法務局が保管し、死後、相続人等に通知してくれるので、大変ありがたいと思います。今後、ますます利用が拡大されていくと思います。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
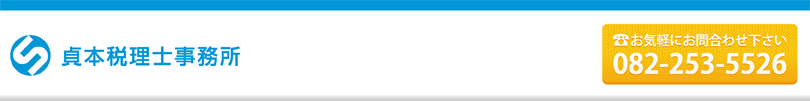



 RSS 2.0
RSS 2.0