税理士日記
税理士日記
一般社団法人等に対する相続税課税制度
2019/10/27 12:11:18
特定の一般社団法人等に対する課税のあらまし
一般社団法人等に対する相続税課税制度が平成30年度税制改正で導入されましたが、改正法施行前に設立された既存法人が課税要件に該当する場合には施行から3年のうちに何らかの対応が必要です。国税庁はこのほど「特定の一般社団法人等に対する課税のあらまし」を公表していますが、特に被相続人の同族理事が過半である場合の課税要件に注意したいです。相続税の課税要件を確認しておくと、対象となる特定一般社団法人等は、(1)相続開始直前にその被相続人に係る同族理事が理事総数の2分の1超、又は(2)相続開始前5年以内のうち3年以上、被相続人に係る同族理事が理事総数の2分の1超であったこと――のいずれかに引っ掛かると、その特定一般社団法人等を個人とみなして相続税を課税する。つまり、(1)の相続直前に同族過半の状態を解消するのでは手遅れなので、(2)の同族過半の状態を3年未満のうちに解消しておく必要があるわけです。
ここで既存法人の取扱いが気になるが、改正法の経過措置では、施行前の平成30年3月31日以前はこの過半要件を判定する期間に含まないとしており、国税庁の情報においても、令和3年の3月末までに同族過半要件を解消すればよいことが分かります。既存法人は同族要件に該当する理事の有無を確認しておきたいところです。
一時期、一般社団法人等を利用した相続税の節税策として流行りましたが、メスが入っております。早めの対応が必要です。
ふるさと納税状況
2019/09/20 10:13:17
ふるさと納税 増加続く
総務省がこのほど公表した最新のふるさと納税に関する現況調査結果によると、今年3月末までの平成30年度中に全国の地方団体が受け入れたふるさと納税による寄附金の額は5,127億円にのぼり、前年度に比べ1.4倍となったことが分かりました。受入額では、平成25年度から6年連続で右肩上がりの増加を示す結果となりました。都道府県別では、受入額が最も多かったのは大阪府の約656億円で、府下の泉佐野市の497億円余、熊取町の76億円余の2市町でその大半を占めました。泉佐野市は全国の市町村の中で最も多く寄附金を受け入れています。続いて受入額が多かったのは北海道の約503億円。道下の森町の59億円余、根室市の49億円余、八雲町の36億円余が主だったところです。北海道に続いて受入額が多かったのは佐賀県で約424億円。県下のみやき町の168億円余、上峰町の53億円余、唐津市の34億円余などが受入額を押し上げました。
問題となっている返礼品の調達費用は全地方団体の合計で1,814億円ほどかかっており、全体の寄附金受入額5,127億円に占める割合は35%強にのぼりました。平成30年度においては返礼割合の目安とされる3割を超えていたことが浮き彫りとなりました。
これに対して、令和元年度における個人住民税の課税においては、ふるさと納税による寄附金4,576億円余のうち3,264億円余が税額控除されています。うち、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用も965億円余に及び、いずれも前年度より増加していることも分かりました。
我家では、ふるさと納税でお肉、果物、お米などが送られてくると、家族全員が笑顔になります。いつ送られてくるか本人も忘れており、不意をついて品物が届くという実感です。なかなか面白いですね。
楽しい制度だと思いますので、ゆったりと継続してほしいですね。
配偶者居住権・遺留分侵害額請求など
2019/08/28 14:30:10
配偶者居住権や遺留分侵害額請求などの税務上の取扱い
民法・相続分野の改正を踏まえた課税関係について、国税庁は、配偶者居住権が合意で消滅した場合にはみなし贈与課税する一方で、配偶者死亡による消滅には課税が発生しないこと、特別寄与料が支払われた場合の取扱いを相続税法基本通達に新設したほか、本年7月に遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと改正されたことに伴う資産移転には譲渡所得の課税が発生することを所得税基本通達に新設しています。配偶者居住権の消滅については、配偶者居住権を取得した配偶者と配偶者居住権の目的となっている建物の所有者との間の「合意」若しくは配偶者による「配偶者居住権の放棄」、建物所有者による「消滅の意思表示」により消滅した場合の課税関係が通達化されています(相続税法基本通達9−13の2)。消滅した際に建物所有者や建物敷地の所有者が対価を支払わなかったとき、又は著しく低い価額の対価を払ったときは、原則、消滅直前の配偶者居住権の価額に相当する利益等を、配偶者から贈与されたとして課税されます。
これに対して、配偶者居住権の期間満了や配偶者死亡による使用貸借の終了、賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了に伴う配偶者居住権の消滅にはこの取扱いがないとしており、課税関係が発生しないことが明記されました。つまり、配偶者死亡の二次相続では配偶者居住権は評価されないため、自動的に一次相続より評価額が下がることになります。相続税対策として配偶者居住権が活用されることが見込まれます。
また、本年7月1日に施行された改正民法により、遺留分減殺請求から遺留分侵害額という金銭債権の請求に代わったことに伴う課税関係は所得税基本通達の譲渡所得関係で明確化されています。
具体的には、民法1046条1項による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合に、(本来の)金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部を履行するために資産の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行時にその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなるという取扱いが新設されました(所得税基本通達33−1の6)。この場合、譲渡による収入金額は、遺留分侵害額にかかる債務の消滅額となるわけです。
これに対して、遺留分侵害額の請求を行い、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産の移転を受けた者は、原則、その履行時に消滅した債権の額に相当する価額により当該資産を取得したことになります(所得税基本通達38−7の2)。この価額が移転を受けた資産の取得費となるわけです。
配偶者居住権や特別寄与料や遺留分侵害額請求などは、民法の新しい規定です。まだ、国民になじみがなく、周知が必要です。税務上も新しい取扱いとなるため、慎重かつ丁寧に対応してまいります。
空き家の譲渡特例「被相続人の居住の用に供されなくなる直前」で判断
2019/07/24 09:05:18
空き家の譲渡特例における要介護などの認定時期
相続による空き家の譲渡特例は、令和元年度改正により、被相続人の相続開始直前に老人ホーム等に入居などの特定事由により居住の用に供されなくなった家屋や敷地に適用できるようになりました。特定事由とは要介護や障害支援区分の認定を受ける被相続人が老人ホーム等に入居していた場合ですが、この認定時期がいつなのか、このほど公表された改正通達では「被相続人の居住の用に供されなくなる直前」になることが明確化されました。改正通達に新設された「要介護認定等の判定時期」(措通35−9の2)によると、被相続人が、要介護認定若しくは要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、「被相続人居住用家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、当該被相続人がこれらの認定を受けていたかにより判定する」こととされました。
同じく老人ホーム等に入居中に相続が発生した場合でも一定の要件を満たせば適用できる相続税の小規模宅地特例では、老人ホーム等の入所後に認定を受けた場合や申請中に相続が起きて、その後、認定を受けたケースも特例の対象とする弾力的な取扱いがされますが、空き家譲渡特例はあくまでも、要介護等の認定を受けて老人ホーム等に入所といった場合に限られ、厳格に解釈される点に注意する必要があります。
この特例は、相続税の小規模宅地特例よりも要件が細かく厳しいものとなっています。納税者のうっかりミスなど発生しやすい状況です。もう少し弾力的に使い勝手がよいものになってもらいたいです。それでも、法律の主旨は満たすと思います。
過去の領収書などのスキャナ保存
2019/06/26 18:24:29
過去の領収書などのスキャナ保存
過去の領収書などをスキャナ保存できるようになるほか、税務署に対する申請等の手続も簡素化されます。過去分は令和元年9月30日以後の税務署届出分から適用されます。さらに国税庁が本年7月に予定する通達改正では、スキャナ保存する際のタイムスタンプは受領後1週間以内が要件ですが、「7営業日以内」もOKとするなどの弾力的な運用もありそうです。平成31年度の法令改正を確認すると、一つは、新規開業の個人が最初から電子帳簿保存する際の承認申請書の提出期限の特例が設けられました。電子帳簿もスキャナ保存も、帳簿の備付開始日から3月前に承認申請書を提出するのが原則ですが、新設法人は既に設立の日以後3月以内まで認める特例があり、今回、個人事業者についても業務を開始した日から2月を経過する日までの申請を認める特例が設けられます。
もう一つは、過去分の領収書等のスキャナ保存です。現行法は税務署から承認後に受け取った領収書等から適用されますが、改正により承認を受ける前に作成や受領した領収書等のスキャナ保存を容認します。事前の届出は必要となりますが、過去5年分や7年分の領収書や請求書等を一気にスキャナ保存できることから、保管コストの削減ができます。令和元年9月30日以後に提出する適用届出書に係る過去分の重要書類から適用できます。
電子帳簿の保存は、あまり積極的にはお勧めしませんが、領収書のスキャナ保存は大変助かります。人手があまりかからず領収書をスキャナで保存できるのであれば?、ありがたいです。場所もとらないため、よいことだと思います。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
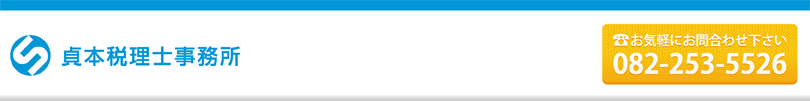



 RSS 2.0
RSS 2.0