税理士日記
税理士日記
配偶者居住権
2020/03/23 15:21:51
配偶者居住権の設定後の相続・遺贈・贈与
改正基本通達を見ていくと、配偶者居住権が設定された時における配偶者居住権の存続年数に応じて法定利率による複利の計算で現価を算出していきますが、この法定利率は、配偶者居住権が設定された時における民法404条が定める法定利率をいうことも明らかにしています(相基通23の2−4)。法定利率は3年ごとに見直されますが、配偶者居住権等の評価においては、配偶者居住権が設定された時における法定利率、つまり、配偶者居住権が設定された日に適用される法定利率を用いることになります。さらに配偶者居住権等を評価する際の「平均余命」は、厚生労働省作成の「完全生命表」の年齢や性別に応じた平均余命(6月以上の端数は切り上げ、6月未満の端数は切り捨てた年数)となりますが、この完全生命表は5年ごとに改訂されています。そこで改正通達は、配偶者居住権が設定された時の属する年の1月1日現在において公表されている最新のものによることを明らかにしました(同23の2−5)。
配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した配偶者居住権の目的となっている建物及びその建物の敷地の用に供される土地の取得時の価額(同23の2−6)については、配偶者居住権の評価方法に準じて計算することになることも留意的に明記しました。二次相続等により居住建物等を取得した場合の評価方法は法令に規定されていないため、どのように評価すべきか疑義があったことから、配偶者居住権の目的になっている建物やその敷地を相続等により取得した時に、配偶者居住権の設定があったものとして計算することを明らかにしています。
配偶者居住権は、令和2年4月から施行されます。勿論実務でまだ拝見したことはありませんが、一般的なものとなるか、否か 様子を見ております。
いずれにしても、我々実務家にとって注意事項です。
国外財産調書の提出状況
2020/02/22 16:05:01
国外財産調書の提出状況
国税庁の平成30年分国外財産調書の提出状況によると、提出総件数(令和元年6月末までの提出)は9,961件(対前年比4.3%増)、その総財産額は3兆8,965億円(同6.3%増)となり、平成26年1月の制度施行以来増加の一途にあります。国外財産調書は、その年の12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産を保有する居住者が、翌年3月15日までにその財産の種類や数量、価額等を記載して提出するものです。東京国税局管内が6,413件と最も多く64.4%を占め、大阪局1,405件、名古屋局719件、その他が1,424件。また、総財産額も東京局が2兆8,458億円と全体の約4分の3に達し、大阪局5,282億円、名古屋局2,190億円となっており、大阪局が5,000億円、名古屋局が2,000億円を突破しました。
申告財産を主な種類別にみると、最も多いのが「有価証券」の2兆1,135億円で以下、「預貯金」5,771億円、「建物」4,360億円、「貸付金」1,880億円、「土地」1,557億円。ここ数年は有価証券が増加し、預貯金が減少傾向にあります。
一方、平成30事務年度における所得税・相続税の実地調査の結果、加算税の特例が適用された件数は、軽減措置が194件、加重措置が245件となっており、加重措置に伴う増差所得等金額が大幅に増えています。なお、現在国会に提出されている令和2年度税制改正法案では、国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の見直し等が盛り込まれています。
国外に財産を持たれている方が増えています。有価証券などの金融財産が代表的ですが、この度、国税からメスが入りそうな国外の建物を使った節税などをされている方もいらっしゃると思います。 税務署は国外財産の把握にやっきになっているようです。
消費税の還付
2020/01/26 13:52:11
建物の取得に係る課税仕入れを行った日はいつか?
金地金の取引を利用した消費税還付策が最近散見されますが、還付の対象となった建物の取得の日が課税仕入れとなる課税期間か否かが争われていた事案で、東京地裁は「取得日は契約日ではなく引渡日であるため、還付の対象とはならない」と判断しました(平成31年3月14日判決)。不動産賃貸業を営むX社は、平成24年6月に金地金を売買する取引を行った結果、平成25年11月5日〜30日の課税期間(本件課税期間)において課税事業者となりました。本件課税期間中の11月15日にKからマンションの土地建物を9億7,000万円で購入する契約を締結しました。翌課税期間の12月2日に売買代金の全額を支払って登記を行いました。X社は本件課税期間の消費税について、建物部分ほか8億円に係る消費税を控除対象仕入税額に算入した上で申告したところ、税務署から否認されたため裁判に訴えました。
争点は建物の取得に係る課税仕入れを行った日はいつかです。すなわち、契約日である11月15日であれば課税事業者、引渡日である12月2日であれば免税事業者となるため、取得をしたのはどちらの日かが争われました。これについて東京地裁は、売買代金全額の支払と所有権の移転登記は12月2日に同時履行となっていること、契約上、マンションの賃料収入や一切の地位は引渡日をもってX社の帰属となることから、国側の主張する引渡日が課税仕入れを行った日に該当すると判断しました。X社の請求を棄却しました。
この裁判がすべてではないと思いますが、土地建物の取得時期を考える際、十分に注意しないといけません。
経営力向上計画
2019/12/19 12:59:27
経営力向上計画の認定申請をされませんか?
中小企業経営強化税制による即時償却や税額控除、所得拡大税制の税額控除の拡大などのメリットがある「経営力向上計画の認定申請」の作成などの業務をさせていただいております。設備投資についてご検討されているのであれば、お声をかけてください。さらに、その経営計画を達成するように、社外パートナーとしてサポートさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
ふるさと納税
2019/12/19 11:57:06
ふるさと納税
ふるさと納税において寄附者が自治体から受けた地場の特産品などの返礼品について、国税庁は一時所得に該当することを質疑応答事例として同庁のホームページ上で明らかにしていることが分かりました。照会は、ある地方団体がふるさと納税により1万円以上の寄附を受けた場合に、この寄附に対する謝礼として、3,000円程度のその地方団体の特産品を送ることとしているときに、寄附者が受けるこの経済的利益について課税関係は生じるかというものです。
これに対して回答は、「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当」するとし、ただし、3,000円程度の特産品であることから、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じないと説明しています。つまり、一時所得は50万円以上でなければ実際には課税されないことから、この質問のようなケースでは課税関係は生じないというわけです。
ただ、高額所得者の場合には、全国のさまざまな地方団体にふるさと納税を行い、数百万円相当の返礼品を受け取っている納税者もあるということです。そのような納税者においては申告する必要があるのは言うまでもありません。この場合に、一時所得の算定上、通常はその収入を得るために支出した金額を収入から差し引くことができるが、ふるさと納税額は見返りのない寄附であることから、このような処理はできません。基本的には返礼品の合計額から50万円を差し引いた額が一時所得の課税金額となることに留意したいです。
細かく決まると、面倒になりますね。
Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.
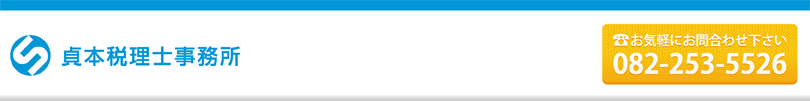



 RSS 2.0
RSS 2.0